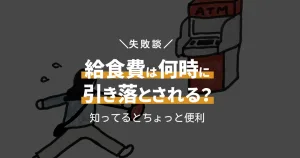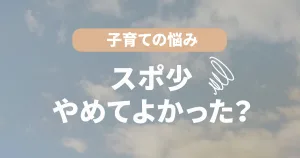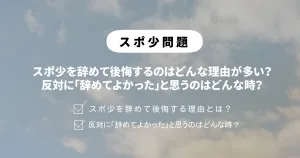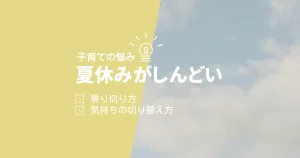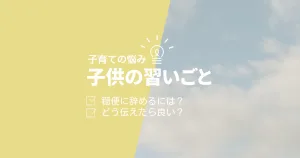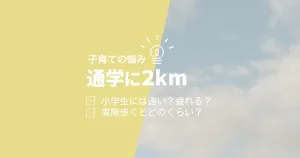筆者
筆者小学生の子供がスポーツをやっています!親としては、練習時間が長すぎる…と感じることがあります



所属する団体によって活動時間は様々ですが、小学生の子供に適した活動時間の目安ってあるんでしょうか??
わが子が約3年間スポーツ少年団に在籍。役員の経験もある筆者の体験談を元に執筆しています。
スポ少とは?
スポ少とは、スポーツ少年団を省略した呼び方です。
スポーツ少年団とは1962年に発足され、単位スポーツ少年団、市区町村スポーツ少年団、都道府県スポーツ少年団、日本スポーツ少年団の4つの段階で構成・運営されています。
また、住民スポーツの総体である体育・スポーツ協会や教育委員会とも連携して青少年の健全育成に努め、以下のような理念を掲げています。
- 一人でも多くの青少年にスポーツの歓びを提供する
- スポーツを通して青少年のこころとからだを育てる
- スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献する
この記事では、スポーツ少年団の呼称をスポ少と記載しています。
スポ少活動の適切な活動量は?
JSPO 日本スポーツ協会【スポーツ少年団とは スポーツ少年団組織と活動のあり方の解説書(pdf)】によると、スポ少(スポーツ少年団)活動の無理のない活動量は、以下のように書かれています。
単位団活動の目安としては、平日では 1 日 2 時間程度、
休日・祝日では 1 日 3 時間程度まで、1 週間に 2、3 回が無理のない活動といえるでしょう。
JSPO 日本スポーツ協会 ガイドブック スポーツ少年団とは スポーツ少年団組織と活動のあり方の解説書(pdf)より引用



親としては練習時間が長すぎると思う一方で、「スポーツするならこれくらいは普通」などと言う保護者の方もいて、悩んでしまう状況もあるあるだと思います。



スポ少活動については以下のように書かれています。
1 回の練習時間は、スポーツの種目によって違いますが、たいていの種目は 1 時間から 2 時間熱心にやれば十分です。
JSPO 日本スポーツ協会 ガイドブック スポーツ少年団とは スポーツ少年団組織と活動のあり方の解説書(pdf)より引用
この際注意しなければならないことは、あまり熱心に毎日毎日やり過ぎたり、だらだらと 3 時間も 4 時間もやったりすると、練習の能率があがらないばかりでなく、団員の父兄からも非難されたり、敬遠されることになりかね
ないので、時間を決めてそれを固く守るようにしてください。



練習時間が長すぎることに加え、土日祝など全て練習試合や遠征で予定が入ってしまうので、スポ少での活動を親の方がしんどいと感じることも当たり前に聞く話でした。



子供のために…という本当にただそれだけの気持ちで皆さん頑張っているのをたくさん見てきました。
実際の活動量は?



実際のところはどれくらいの活動をしているの?
多くの場合、活動量は所属する団体やチームにより異なります。
ちなみにわが子(当時小学生)が所属していたチームの活動量はこんな感じでした。
- 平日5日、土日祝は練習試合or遠征
- 平日の練習は2~3時間、練習試合がない土日のどちらか1日は半日練習



ちなみに海外の友人にも聞いてみたところ、やはり「練習量多すぎ」と回答が。



日本では、勉強や受験もそういった傾向があるように、練習はすればするほど身につくという固定観念があるのかもしれません。
所属するチームや、競技によって違いはあると思いますが、筆者の周りでは週4日程度の活動をしているチームが多い印象でした。
スポ少での長時間の練習による練習しすぎについて
スポ少での練習時間が長くなることで起こりうるメリットとデメリットを紹介します。
メリット
- 練習量の成果が見える
- 仲間・友達との絆が深まる
- 保護者同士の団結にも繋がる



団体競技としては、練習に時間をかけた分「チームとしての結束」やチームメイトとの繋がりは強くなります。
デメリット
- 体や心に負担をかける
- オーバーユース(身体の使いすぎ)によるケガのリスクが高まる
- 身体の成長に悪影響を与えることがある(子供の骨や筋肉は発達途中にあるため)
- スポーツ障害のリスクが高まる
長時間の練習における一番のデメリットは、やはり子供の心身にとっての負担になることです。
特に子供の身体は成長過程であり、過度な練習は怪我のリスクや心身に悪影響を与えます。
さらに普段の練習が長時間になると、毎日の練習だけで精一杯になり、学校や宿題、家族との時間やリラックスするための時間さえなく、子供にとって健全な日常生活を送ることが困難になります。
スポ少の活動時間は誰が決める?



実際には誰がスポ少の活動を決めているの?
わが子が所属していたチームでは、普段の練習時間や練習試合・遠征などのスケジュールを決めていたのはチームのメインコーチでした。
練習時間が長すぎることに対してできること
日本のスポーツをしている子供達の練習量が多すぎることが、今問題視されています。
その背景にあるものは、【練習したらしただけ上手くなる】、逆に【苦しい練習をしなければスポーツは上手くならない】といった価値観がいまだに多くの日本人に根強く残っているからだと個人的に感じていました。



相手チームよりも練習量が少なかったから負けた、だから練習量を増やせば勝てるはず、そのために試合に負けたら帰ってからも急遽練習



はたして本当にそれが正しい方法なのでしょうか…
スポ少の練習時間が長すぎると感じたり、チームのやり方・運営方針に疑問を持つことは悪いことではありません。
ここでは、長時間の練習への対策を紹介します。
- 練習内容や目標の共有
- 1回の練習の質を高める
- 移籍する
もしも可能であるならば、所属する団体やコーチに意見として伝えてみるのが良いと思います。
また、1回の練習を質の高いものにすることで、長時間の練習が不要になる場合もあると思います。
競技をする子供たちのことを一番に考える・大切にする、なおかつ保護者の意見にも耳を傾けてくれる風通しが良いチームであれば理想ですが、残念ながらそのチームのやり方にこだわり、保護者の意見に耳を傾けないチームもいまだに多く存在します。
所属する団体やチームがそのような運営方針の場合、個人の力でチームを変えることはほぼ不可能ですので、移籍やチームを変えるといった方法が良いと思います。
適切な活動量でスポーツをすることのメリット
逆に、適切な活動量でスポーツをすることのメリットを紹介します。
- 体を休めることができる(怪我のリスク、コンディションの良い状態でスポーツに取り組める)
- 学校とスポーツの両立ができる
- 家族との時間が取れる(安定した心があってこそスポーツに取り組める)
- 自発的な意欲につながる(心に余裕がある)
小学生という年齢では特に、健やかな心身の発育がとても大切です。
身体の発育はもちろんですが、安定した心と身体があってはじめてスポーツに取り組めます。
過度な運動は子供の体と心を疲れさせる可能性もありますし、慢性疲労の状態では良いパフォーマンスで競技に取り組むこともできません。



わが子が在籍していたチームは土日祝も基本的には練習試合や遠征だったので、宿題や学校のことが出来ず、チームの練習をこなすことだけ考えているような毎日でした。



このようになってしまうと本末転倒です
わが家の場合、このような長時間の練習は、チームとしての方針であり、子供が自発的にやりたいと言っての練習時間ではありませんでした。
本来であれば、競技をしている子供の「自発的な練習」こそ意味があるはずです。



チームでも団体でも、「個」というものが集まって団体になるはずです。



だからこそ、「個」を大切に扱って欲しい
スポ少活動について思うこと
- 一人でも多くの青少年にスポーツの歓びを提供する
- スポーツを通して青少年のこころとからだを育てる
- スポーツで人々をつなぎ、地域づくりに貢献する
スポーツ少年団が掲げている基本理念にもあるように、子供にとって大切なことは
「楽しい」という気持ちが根本にあることです。
私自身スポ少の活動に参加してきて思ったことは、
「所属しているチームでレギュラーになれないならその競技はやめたほうがいい(才能がない)」
「どうせプロになれないならその競技をやる意味がない」
「(レギュラーメンバーではない子供に)どうせ試合に出ないならその競技をやっても意味がない」
など、まるで大人ができる子・できない子のように子供を選別するような言葉をたくさん聞いてきました。
これが中学、高校という年代になってきたらまた話は違ってくるのかもしれませんが、今回この記事で対象にしているのは小学生という年代です。
大人が結果にこだわり、せっかく芽生えた子供の「そのスポーツが好き」という気持ちをなくしてしまわないような環境作りが大切だと、私自身は強く思っています。
まとめ
私自身、スポーツ少年団に所属した経験の中で、子供がやりたいからという理由で、長すぎる練習時間や厳しいルールの少年団の活動について親子ともに我慢しながら活動を続けている保護者の方をたくさん見てきました。
小学生のスポ少は親の送迎や遠征の手伝いなど、子供だけでは活動ができないという組織の特性が少なからずあります。
そのため、親がスポ少での活動がしんどいと感じていたり、無理や我慢を続ける姿を、子供はずっと見続けることになります。
そのため、長時間の練習のメリット・デメリットなどを親子で話し合い、家族や子供にとって最良の選択を考えていくことが大切だと思います。
それでは